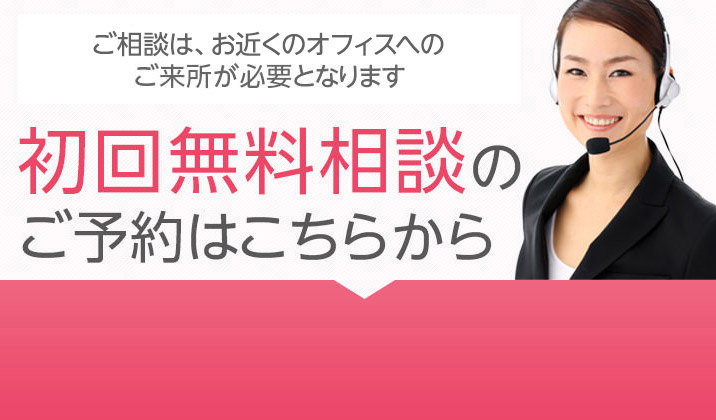元旦那・嫁からの嫌がらせは違法の可能性も? 対処法や弁護士に相談すべき理由を解説
- その他
- 元夫
- 嫌がらせ
- 大阪

大阪府の令和5年の離婚件数は1万4556 件で、年々減少傾向にあるものの、全国的に見ると比較的高い離婚率となっています。
離婚に至るまでには、お金や子どもに関するさまざまな問題を解決しなければなりません。しかし、さまざまな問題を解決してやっと離婚が成立しても、元旦那・嫁の嫌がらせに悩まされ続ける方も少なくないようです。
本コラムでは、元旦那・嫁からの嫌がらせがある場合、どういった行為が違法となるのか、嫌がらせへの対処法について、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。


1、元旦那・嫁からのよくある嫌がらせ
まずは、元旦那・嫁からの嫌がらせでよくあるケースをみていきましょう。
-
(1)メールや電話での嫌がらせ
元旦那・嫁から執拗なメールが送られてくる、何度も電話がくる、というケースがあります。そればかりか無言電話をかけてくる、暴言や脅迫まがいの内容のメールが送られてくるケースもあるようです。
また、自身に対する嫌がらせにとどまらず、実家や再婚相手にまで被害が及ぶこともあります。
さらに、SNSに離婚話の詳細や悪口、誹謗中傷などを書き込まれ、トラブルに発展することもあるようです。 -
(2)職場の同僚に作り話をするなど、名誉を毀損する嫌がらせ
元旦那・嫁が同じ職場で働いていたり、共通の友人・知人が多かったりする場合、職場の同僚や共通の知人に対して自身をおとしめるような作り話をするケースがあります。
こうした言動は、職場での立場に大きく左右し、また、友人関係の破綻にもつながりかねません。 -
(3)つきまとい・ストーカー行為による嫌がらせ
離婚後、元旦那・嫁がつきまといやストーカー行為に及ぶというケースは少なくありません。
ストーカー規制法において、次のようなつきまとい等およびストーカー行為が規制対象となっています。つきまい等とは、以下に挙げるような行為類型のことであり、ストーカー行為は、つきまとい等を繰り返して行うことです。
- 「つきまとう」「待ち伏せする」「自宅などを見張る」「自宅付近などをみだりにうろつく」「自宅などに押しかける」行為
- 「監視している」と告げる行為
- 面会や交際を要求する行為
- 著しく粗野または乱暴な言動をする行為
- 無言電話、拒否した後に連続した電話・メールなどを送付する行為
- 汚物などを送付する行為
- 名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心を侵害する行為
2、元旦那・嫁の嫌がらせへの基本的な対処法とは
元旦那・嫁からの嫌がらせに対しては、以下のような対処法が考えられます。
-
(1)相手にしない
元旦那・嫁からの嫌がらせに対して反応すると、その反応欲しさに、さらに行動がエスカレートする危険性があります。直接連絡を取ることなく、相手にしないという姿勢でいることが望ましいでしょう。
-
(2)連絡をとれないようにする
メールや電話での嫌がらせに対しては、「メールアドレスを変える」「着信やメールの受信を拒否する」「携帯電話や固定電話を解約して番号を変える」など、連絡をとれないように対処するとよいでしょう。
その際、共通の友人・知人がいる場合は、新しいメールアドレスや電話番号を、元旦那・嫁に伝えないよう、協力を求めることも必要です。
また、SNS上での嫌がらせの書き込みなどに対しては、管理者に削除請求を行うなどの方法で対処することができます。 -
(3)証拠を残しておく
嫌がらせのメールを保存しておく、電話を録音しておくなど証拠を残しておくと、警察や弁護士に相談する場合に有利に働きます。
「証拠になるかわからない」というものであっても、後々役に立つ可能性があるので、できる限り意識して証拠を残しておいてください。 -
(4)危険を避けるように行動する
元旦那・嫁からの嫌がらせがある場合は、危険を避けるように行動することを心掛けるとよいでしょう。危険を避ける行動としては、できるだけひとりで行動しないことや連絡先などの個人情報が漏れないようにゴミ出しにも注意することなどが考えられます。
また、防犯カメラを設置するなどの対策もよいでしょう。
お問い合わせください。
3、つきまとい・ストーカー行為があれば早めに警察へ相談を
元旦那・嫁のつきまといやストーカー行為は、ストーカー規制法の規制対象となりえます。
警察に申し出ることで「警告」や「禁止命令」を出してもらえる可能性があります。それらが出されても、元旦那・嫁が行為をやめない場合、逮捕されることになります。
警告とは、つきまとい等をやめるよう、警察が書面や電話などで警告を行うことです。この場合、法的な強制力はありません。
禁止命令とは、都道府県公安委員会がつきまとい等をやめるよう、加害者に命令するものです。禁止命令には法的な強制力があり、被害者からの申し出により、加害者への聴聞を経て、禁止命令が発令されます。
ただし、被害者の身の安全がおびやかされ、緊急の必要がある場合には、事前に加害者に聴聞または弁明の機会を与えなくても、禁止命令を出してもらうことが可能です。
ストーカー規制法に違反してストーカー行為をした加害者には、最大で2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。つきまとい・ストーカー行為を放置すると、深刻な被害につながる可能性があるため、該当する行為の被害にあっていれば早めに警察に相談してください。
4、元旦那・嫁の嫌がらせについて弁護士に相談すべき理由
元旦那・嫁からの嫌がらせに対しては、弁護士に相談することも重要な選択肢となります。弁護士がどのように対応してくれるのか確認しておきましょう。
-
(1)内容証明郵便を送付してけん制することができる
弁護士は、元旦那・嫁に対してストーカー行為などの嫌がらせをやめるように求める内容証明郵便を弁護士の名で送付することができます。
弁護士の名で内容証明郵便が送付されることで、元旦那・嫁に対して大きなプレッシャーを与え、嫌がらせをけん制できると期待できます。 -
(2)代理人として元旦那・嫁と交渉することができる
弁護士は、元妻の代理人として元旦那・嫁と交渉することができます。
ご自身で対応すると、精神的に大きな負担を感じるだけでなく、嫌がらせがエスカレートする場合もあります。弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として元旦那・嫁に交渉するため、直接会わずに話し合いを進めることができます。 -
(3)弁護士を通して警察に相談することができる
嫌がらせやストーカー被害を警察に相談しても、ご自身だけでは警察を動かすことができない場合があります。そういった場合でも弁護士に相談すれば、弁護士が代理人として警察に的確に説明し、法的な対処を求めて働きかけることが可能です。
その結果、警察が本格的に対応してくれる可能性が高くなります。 -
(4)慰謝料請求などの民事訴訟も対応できる
元旦那・嫁の嫌がらせに対しては、民事訴訟などで慰謝料や損害賠償を請求できるかもしれません。
裁判になった場合、弁護士は、裁判でも専門家として法的見地から依頼者の有利になるような主張や立証をすることができます。 -
(5)あらゆる法的手段を検討できる
元旦那・嫁から嫌がらせを受けているケースの中には、子どもへの養育費が支払われていないなどの問題を抱えているケースも少なくありません。
弁護士に依頼することで、嫌がらせに対する法的な対応だけでなく、養育費の不払いなどの問題についても適切な法的手段をアドバイスしてもらえます。
また、子どもへの影響を考慮して元旦那・嫁に対して警察沙汰にしたくないという思いがある方もいるでしょう。そうしたケースについても、弁護士は依頼者の要望に沿った法的手段を検討します。
お問い合わせください。
5、まとめ
元旦那・嫁の嫌がらせの内容によってはすぐに警察に相談した方がよい場合もありますが、弁護士に相談すればあらゆる法的手段の検討が可能になります。弁護士から警察に相談することもできるため、迷ったら弁護士に相談するのもよいでしょう。
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士は、ご相談者の立場に立って問題を解決できるように全力でサポートします。ぜひお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています