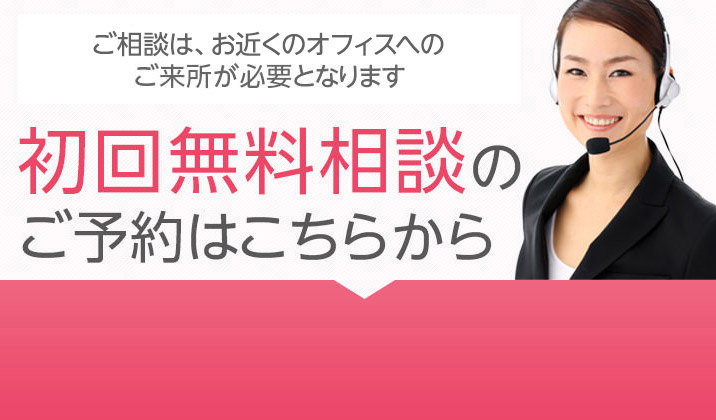子ども2人の養育費はどう計算する? 親権が分かれたらどうなるの?
- 養育費
- 養育費
- 2人
- 大阪
- 弁護士

離婚話を進めていくにあたって、養育費についても考える必要があります。たとえば、子ども2人の家庭の場合、養育費はどのぐらいになるのでしょうか。また、父が兄を、母が弟をといったように、子どもの親権が分かれたとき、養育費はどうなるのでしょうか。
本コラムはでお伝えすることは、大きく以下の3つです。
・ 子ども2人の養育費は、親の収入や子どもの年齢によって算定され、裁判所の養育費算定表をもとに決定する。
・ 親権が分かれた場合、監護権を誰が持っているか、つまり実際には誰が育てているかを基準に考え、生活費指数を用いて養育費を計算する。
・ 一度決定した養育費は、収入の変動や再婚などで変更も可能であり、子どもの健全な成長のために適正な養育費を決めることが重要。
本コラムでは、養育費を決める手続きや算定方法について、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。


1、そもそも養育費とは?
離婚すれば夫婦が別々に暮らすことになります。つまり、今まで両親と一緒に暮らしていた子どもは、片方の親とは離れ離れの生活になってしまうわけです。
このように、離婚などの事情によって一方の親と離れて暮らすこととなった未成熟な子どもの養育に必要な費用として、離れて暮らす親が負担する費用を養育費といいます。
親族はお互いに助け合うものと考えられており、その関係性によって、助けるべき義務の程度に違いがあります。
親子間の場合、助け合いの程度は「生活保持義務」とよばれるもので、もっとも程度の高い義務です。これは、最低限の生活ができればいいというものではなく、離れて暮らす親と同じ程度の生活レベルを子どもに維持させる義務といえます。
したがって、たとえば父親が高収入の夫婦が離婚し、母親が子どもの親権を得て育てる場合、父親が支払う養育費の金額は高くなります。離婚せずに同居していれば、その親の収入を前提として生活していたわけですから、養育費は、あくまで親の収入を基礎として計算することになっているのです。
2、養育費の決め方
それでは、実際に養育費を定めるときは、どのように行うのでしょうか。
-
(1)夫婦間の協議で決める方法
養育費は、離婚の際に夫婦で話し合って、決めることができます。特に話し合うべき点は以下のとおりです。
- 具体的な金額:月ごとの支払い金額
- 支払方法:現金手渡し、振り込み、振り込みの場合はどの口座にするのか、など
- 支払日:毎月月末など
- いつまで払うのか:子どもが成人するまで、大学を卒業するまでなど
また、進学や留学、病気などで特別な出費が見込まれる場合には、その場合の費用負担について、あらかじめ決めておくこともできます。
協議で決めた場合は、書面で作成しておくことで後々のトラブルを避けることができます。特に、公正役場で公正証書を作っておけば、支払いを受ける側は安心です。
公正証書に、相手が支払わなくなった場合には、強制執行をされても構わないという内容の文言を入れることで、その公正証書を根拠として、将来の不払い時に差し押さえなどの強制執行が可能となります。
もっとも、離婚する夫婦の間で、養育費をはじめとする金銭的な内容を冷静に話し合うことは、難しい場合があります。特に、養育費だけでなく慰謝料や財産分与などでもめている場合は、感情論が話し合いをさえぎってしまうこともしばしばあります。
このような場合は、次に解説する家庭裁判所の調停制度を用いることが一般的です。 -
(2)養育費請求調停の利用
養育費について話し合いがまとまらない場合は、離婚が成立しているか否かによって、調停の対応が多少異なります。
- ① 離婚が成立してから養育費を決める場合……子どもの監護に関する処分(養育費請求)調停事件として申し立てる
- ② 離婚自体が成立しておらず、離婚調停と合わせて話し合いたい場合……夫婦関係調整調停(離婚調停)の中で、養育費についても話し合う
調停は、家庭裁判所という場を用いた、話し合いの場所であり、裁判官が一方的に金額を取り決める場所ではありません。したがって、ここでもお互いの意見を聞いたり、譲ったりすることが求められます。
具体的には、同じ日に父と母とが裁判所に呼び出され、ひとりずつ交互に調停室に呼ばれて調停委員から話を聞かれ、合意が得られれば、その合意内容を記載した調停調書が作成されます。 -
(3)調停で合意できない場合の手続き
合意できない場合、上記①②のそれぞれの場合によって、その後の流れが変わります。
- ① の場合、調停は不成立で終了し、自動的に審判手続が開始されます。審判では、裁判官が、一切の事情を考慮し、相当と考える養育費について決定を下すことになるのです。
- ② の場合、原則として審判手続に移行しません。離婚訴訟を提起し、その中で養育費を請求することになります。
ただし、②の場合は、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停(婚姻中の夫婦の一方+子どもの生活費を請求する調停です。)を申し立てることが多く、婚姻費用の合意ができず婚姻費用分担調停が不成立で終了すると審判に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮し、相当と考える婚姻費用について決定を下すことになります。
お問い合わせください。
3、養育費の算定方法
養育費の計算は、以下のような、さまざまな考慮要素を基礎として決定されます。
- 養育対象となる子どもの年齢と人数
- 双方の親の収入金額
- 双方の親と子どもの最低生活費と子どもに充てられるべき生活費
- 親の養育費負担能力
家庭によって状況は異なるものの、裁判所が公開している標準的な養育費の金額を一覧表にした養育費算定表で、おおよその金額を確認することも可能です。
実際には、各家庭の実際の事情に応じて上下しますが、ベリーベスト法律事務所も養育費算定表を参考にした養育費計算ツールをご用意しているので、参考としてご利用ください。
4、子ども2人の場合の養育費の計算
子ども2人のケースについて、ベリーベスト法律事務所の養育費計算ツールを使ってシミュレーションしてみましょう。なお、いずれも、妻が子どもを監護しているケースとします。
- ① 子どもが8歳と5歳、妻はパートで年収100万円、夫は会社員で年収は500万円の場合
→養育費は月々6万円~8万円/月 - ② 子どもが8歳と15歳、夫婦ともに会社員で妻の年収300万円、夫の年収が700万円の場合
→養育費は月々8万円~10万円/月 - ③ 子どもが15歳と17歳、妻は会社員で年収250万円、夫が自営業で年収1000万円の場合
→養育費は月々20万円~22万円/月
原則として、以下のようなケースでは、養育費が高くなる傾向にあります。
- 監護親(この場合の妻)の年収が低い
- 非監護親(この場合の父)の収入が高い
- 子どもの数が多い
- 子どもの年齢が高い
上記が目安となりますが、さらに、子どもが私立学校に行っている場合などさまざまな事情を考慮して、最終的な金額が決定されます。
5、親権が分かれた場合、養育費はどう計算する?
養育費算定表は、片方の親が子ども全員を監護しているケースのみを対象として作られています。したがって、親が監護権を分け合っているケースでは、養育費算定表で金額を算出できません。
では、複数いる子どもの親権が父母で分かれた場合、養育費はどのように計算するのでしょうか。
-
(1)親権と監護権
子どもが複数いる場合、父母で親権が分かれる場合があります。また、親権とは別に、実際に同居して育てる権限である監護権を定めることもできます。
たとえば、親権者としては父親が権利を持ちつつ、監護権は母が持つというケースもあります。 -
(2)監護権が分かれた場合の養育費計算
養育費は、実際に子どもを養育しているという実態から生まれる費用なので、親権の所在ではなく、監護権を誰が持っているか、つまり実際には誰が育てているかを基準に考えます。
では、監護権が父母で分かれた場合、つまり、子どもが2人いて、子どもの1人は母が育て、もう1人は父が育てるという場合には養育費をどう計算するのでしょうか。
この場合は、養育費算定表の考え方の基礎となっている「生活費指数」を用いて、具体的に計算する必要があります。生活費指数は以下のとおり定められています。
- 成人:100
- 15~19歳の子ども:85
- 0~14歳の子ども:62
たとえば、以下のような条件で考えてみましょう。
- 子どもの人数:2人
- 子どもの年代:16歳(生活費指数:85)と10歳(生活費指数:62)
- 父母の年収:父が600万円、母が200万円
- 父母の職業:父は会社員(給与所得者)、母も会社員(給与所得者)
- 監護権:父が16歳の子ども、母が10歳の子ども
まずは、母親が2人とも養育するという前提で養育費を計算すると、養育費の範囲は養育費算定表によると毎月8万~10万円となります。仮に、母親が2人とも養育する場合、父親は9万円の養育費を支払う、としましょう。
ひとつの考え方としては、この金額に生活費指数を用いて計算を進めます。養育費9万円を子ども2人で分け合うわけですが、その分ける割合が「生活費指数=85:62」となります。
父親が負担すべき養育費は、母親と暮らす10歳の子どもの養育費であるため、以下のように計算されます。
9万円÷(85+62)×62=約3万7959円
養育費は、毎月およそ3万8000円程度となり、これを毎月送金することになります。なお、計算方法については他の考え方もありますので、上記計算は一例です。
6、養育費の変更は可能?
一度決まった養育費であっても、何かしらの事情の変更があった場合には、養育費の額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。
もっとも、事情変更として認められるためには、多少の生活の変動では足りません。たとえば、継続的に収入が無くなった、父が再婚して新たに子どもができた、母が再婚して子どもが養子縁組をしたなどの事情があれば、変更が認められる可能性が高いといえます。
お問い合わせください。
7、まとめ
養育費は、子どもが健全に育っていくために大切な費用ですから、離婚の際にはきちんと決めてトラブルがないようにしたいものです。しかし、離婚の話し合いを進める中で、夫婦で冷静に相当な金額を決めることはそう簡単ではありません。
また、養育費算定表は、幅のある数字で表示されるため、実際にいくらにするかは、交渉の余地があります。さらには、子どもが私立に行っている場合、大学院や高度な教育を予定している場合、親が自営業で収入の算定が複雑である場合など、各家庭の事情によって、算定自体が難しい場合も少なくありません。
このような場合、養育費が決まらずに離婚が進まない、トラブルが複雑化することでお互いが疲弊する、最終的には子ども自身の大きな負担になってしまうなどのリスクにもなります。
離婚や養育費でお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスまでご相談ください。詳しく状況をお伺いして、適切な金額での速やかな解決を目指します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています