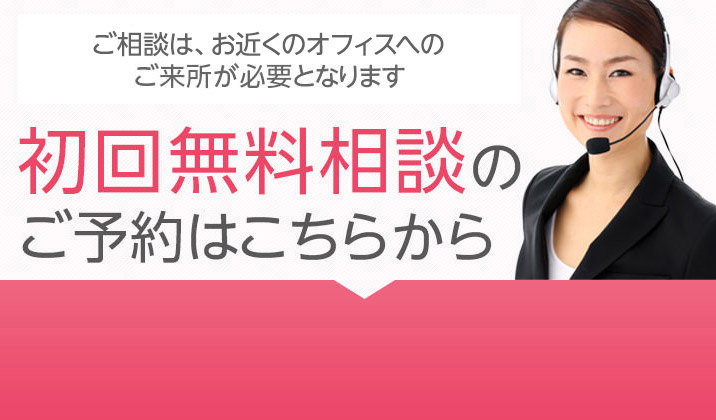借金は財産分与に含まれる?対象の借金や計算方法を解説
- 財産分与
- 離婚
- 財産分与
- 借金

「令和5年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」によると、大阪府では1年間で1万4556組が離婚しました。年々減少傾向にはありますが、全国的に見ると比較的多い件数となっています。
離婚の際にはさまざまなことを取り決めなければなりません。中でも大きなトラブルに発展しがちなのが財産分与です。プラスの財産だけであればスムーズに話し合いが進められますが、家のローンなどマイナスの財産がある場合はどうなるのでしょうか。
本コラムでは、財産分与とはどのようなものなのか、夫婦に借金が残っている場合に財産分与は認められるかなどついて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が説明します


1、財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する手続きのことです。
民法第768条(財産分与)
- 第1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる
- 第2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚のときから2年を経過したときは、この限りでない
- 第3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める
財産分与は離婚するすべての夫婦に認められた権利です。話し合いで分割内容が合意できなければ、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることもできます。
分割する割合は原則として2分の1で、専業主婦(夫)であっても、財産分与を受けることが可能です。
なお、不貞行為をした側など有責となった配偶者側も財産分与によって財産を受け取ることができます。
-
(1)対象となる財産
財産分与の対象となる財産は、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。現金や預貯金、車、不動産、家財道具などが該当します。これらの財産の名義が夫婦共同ではなく、どちらか片方の名義であったとしても、財産分与の対象となる「共有財産」とみなされます。
ただし、結婚前から所有している預貯金や不動産は財産分与の対象外です。また、それぞれの親から贈与を受けた土地やお金も財産分与の対象外となるので注意が必要です。 -
(2)財産分与の種類
財産分与には以下の3つの種類があります。
● 清算的財産分与
一般的に財産分与というと清算的財産分与のことをさします。双方で合意した分割割合に応じて、すべての共有財産を分配します。
● 慰謝料的財産分与
夫あるいは妻が離婚となる原因を作った場合の財産分与では、分与の割合に慰謝料の意味合いを持たせることがあります。これを慰謝料的財産分与と呼びます。
● 扶養的財産分与
離婚をすることによって将来の生活が苦しくなる場合の財産分与です。収入の多い側が少ない側へ一定期間金銭を支払う形で、援助を目的とした財産分与を行うことがあります。
扶養的財産分与に関しては、子どもの養育費の支払いのように法律上明文化されておらず、実際に扶養的財産分与が行われることは少ない傾向にあります。
2、借金は財産分与の対象になる?
財産分与にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産である借金も含まれます。マイナスの財産は、内容によって財産分与の対象か異なります。
-
(1)財産分与に含まれる借金
消費者金融やクレジットカード会社のカードローン、夫婦で生活するために借り入れた住宅ローン、自動車ローンなどの借金も財産分与の対象です。貯金などのプラス財産から、借金などのマイナス財産を引いて残った金額が、実際の財産分与として分配されることとなります。
-
(2)財産分与に含まれない借金
一部の借金は対象外となります。結婚前からの借金や、夫婦どちらかのギャンブルや遊興費などのためにした借金です。これらの借金は、債務者本人が全額返済しなければなりません。
3、財産分与の計算方法
まずは、婚姻期間中に協力して作り上げた財産のうち、前述した財産分与の対象となる財産すべてをリストアップし、プラスの財産がいくらになるのか計算します。不動産の査定額を調べたり、通帳のコピーをとったりなど手間がかかるため、早めに準備したほうがよいでしょう。
次に、借金やローンの総額を算出します。最後に、プラスの財産の総合計額からマイナスの財産の総合計額を引いて残った金額について、分割する割合を話し合って決めます。
専業主婦(夫)で、家庭を築いてからの収入が一切ないという側でも、財産分与の請求はできますし、受け取る権利もあります。割合は原則2分の1ずつです。
ただし、当事者双方が合意すれば4:6でも0:10でも構いません。清算的財産分与や扶養的財産分与の考え方から、3:7となることもあります。分配する際は、金銭などはそのまま決められた割合で分配します。
しかし、不動産や車などは離婚後にどちらかの単独所有とすることが多くなるため、所有した側からその分の金銭を支払うことになるか、売却して金銭に夫婦で分けることになります。
-
(1)財産分与の基準日
財産分与はどの時点での金額を算出するかについて解説します。
原則は、離婚が成立した日が基準日です。
つまり、離婚が成立した日の通帳に記載されている残高や、成立した日の借金額が、財産分与を計算する際の数字となります。ただし、別居している場合は別居日が基準日となります。
不動産や株式などの評価額は、別居時ではなく、離婚が成立したときや調停が成立したとき、または訴訟の口頭弁論が終了したときが基準日になります。 -
(2)財産分与の計算例
では財産分与の計算例をみてみましょう。
● 財産が金銭の100万円のみ(割合は1:1の平等)
夫:50万円
妻:50万円
● 財産が金銭100万円、不動産100万円の価値で総合計額が200万円(割合は1:1の平等)
夫:不動産(100万円)
妻:金銭(100万円)
● 財産が金銭100万円、車が70万円、借金が30万円で総合計額が140万円(割合は1:1の平等)
夫:車70万円
妻:金銭70万円
上記例では、計算の結果プラス財産が残った場合ですが、計算の結果、プラスの財産を全額借金の返済に充当しても、マイナスになり借金が残った場合はどうなるのでしょうか?
● 金銭100万円、不動産100万円、(生活費の補充で借りた)借金が300万円
この場合は、金銭全額と不動産を売却しても、100万円の借金が残ってしまいます。プラスではなく、マイナスになるため、分配できる財産はありません。
借金だけが残る場合は、ふたりで借金を返済するのではなく、借金を借りた本人に返済義務が生じるのが原則です。名義人ではない方は連帯保証人になっていなければ、返済義務は発生しません。
つまり名義人ではない方の当事者は財産分与としてもらえる財産もなければ、借金の返済義務を負うこともないという結果になります。
お問い合わせください。
4、財産分与の進め方
財産分与は次の進め方で行います。
-
(1)夫婦間での協議
財産分与については、まずは当事者で話し合い、対象となる財産や分割する割合を決定します。話し合いで合意した場合は、合意内容を書面化しておきましょう。
決めた通りに分配されなかった場合に備えて、強制執行認諾条項を付けた公正証書を作成することをおすすめします。 -
(2)調停での協議
当事者間での話し合いで結論が出なかった場合には、家庭裁判所に対して「財産分与の調停」を申し立てます。調停では調停委員と呼ばれる人が当事者の言い分をそれぞれ聞き、場合によっては資料を出させるなどして、双方にとって妥当な案を提示してくれます。
調停で双方が合意した場合は調停調書が作成されます。調停調書には裁判の判決と同じ効力があるため、相手が決められた通りに分配しなければ、速やかに差し押さえなどの手続きを取ることが可能です。 -
(3)裁判
調停でも合意ができず、結論が出なかった場合には、自動的に財産分与の審判という手続きに移ります。裁判官がこれまでの事情をもとに、結論を出します。審判で出される結論は必ずしも双方が合意したものではありません。不服がある場合は即時抗告という手続をとることができます。
財産分与は離婚の話し合いと同時並行で進めることが多く、離婚自体に争いがある場合は離婚の調停で財産分与も話し合われることが少なくありません。離婚することに双方異論がない場合は、先に離婚を成立させることもできますが、離婚が成立してしまうと、密に連絡を取ることが難しくなり、話し合いに支障をきたします。
また、財産分与の請求時効は2年なので、離婚が成立した時点で時効のカウントダウンが開始してしまいます。スムーズに財産分与を進めるためには、離婚の諸問題と同時に話し合うことを強くおすすめします。
5、まとめ
財産分与は離婚問題の中でも、大きなお金がやりとりされるためトラブルに発展しやすいものです。多くの人は慰謝料や養育費などに注目する傾向があるようですが、財産分与をおざなりにしておくと、あとで受け取るべきお金を受け取れずに泣き寝入りすることになってしまいます。
これから離婚を考えている方、離婚の話し合い中の方はまずは弁護士に相談した上で、適切な財産分与が行えるようにアドバイスを受けましょう。ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスへ気軽にご相談ください。財産分与問題の取り扱い実績が豊富な弁護士が親身になって対応します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|