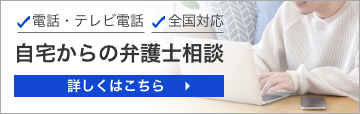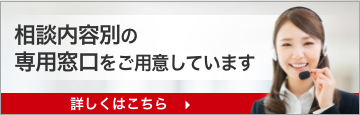著作権を侵害しない引用ルールとは? 企業担当者が知っておきたいポイント
- 商標・特許・知的財産
- 引用
- 著作権
- ルール

近年、著作権侵害事件は増加していますが、著作権違反は、意図せず起こしやすい事案ともいえます。
たとえば、インターネットで見かけた画像を無料素材と勘違いするケースもあとを絶ちません。結果、あとから違約金を含めた高額な著作権使用料を請求される可能性もあります。
さらに、企業が画像や文章を無断利用してしまうと、「パクリをしている企業」と名指しされる可能性もあります。つまり、企業イメージが大きく損なわれるリスクもあるのです。
著作権については「知らなかった」では済まされません。主にウェブサイト制作における著作権を侵害しない画像や文章の引用ルールについて、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、著作権フリー素材を利用する際の注意点
自社の商品・サービスの広告やサイトを制作する際には、より的確にイメージを伝えるための画像や文章が不可欠です。ネット検索などでイメージに合うものを探すこともあるでしょう。しかしその場合は、必ず利用規約を確認しなければなりません。
なぜなら、「著作権フリー」と書いてあっても使用条件が設定されているケースや、そもそも著作権フリーという言葉で検索して見つけた素材であっても、たまたま検索で上位に挙がっているだけで著作権フリーではない素材である可能性があるためです。
著作権フリー素材であっても、利用する前には必ず利用規約を確認してください。商用利用や加工を禁じている場合や、使用する際に著作権を示すクレジット表記を義務付けているところもあるでしょう。
その他にも、使用目的によって使用不可とする利用規約などもあります。たとえば宗教や暴力、ドラッグ関係、出会い系サイトへの使用禁止や、人物写真を体験談に使用することを禁じているケースもあります。
利用規約には、違反した場合の違約金なども規定してある場合があります。利用規約が公開されている以上、知らなかったというのは理由になりません。それらの規定に従って違約金を支払う必要が生じるでしょう。
2、著作権とは?
そもそも著作権とは、どのような権利で、いつ発生し、どのように権利を主張できるものなのでしょうか。
-
(1)著作権
著作権とは、知的財産権(知的所有権)の一種です。主に、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利を指します。
また、日本においては、著作物が創作された時点で自動的に著作権が発生するものとされます(著作権法第17条2項)。これを無方式主義と呼びます。 -
(2)著作物と著作者
「著作物」とは、何らかの思想・感情を文章や音楽、絵画などで表現したものをいい、頭の中に思っているだけでは存在を認められません。それを形にして初めて著作物とされます。
この著作物を創作した人が「著作者」です。たとえ、作品が幼児の描いた落書きであっても、その幼児を著作者として、作品は著作物とされます。誰かが意図をもって書いた図画や文章であれば、どこで見つけた素材であろうとすべてに著作権があることを覚えておきましょう。 -
(3)著作者人格権と著作権(財産権)
著作者の権利は、大きく分けて著作者の人格利益を保護する「著作者人格権」と財産的利益を保護する「著作権(財産権)」から構成されます。
著作者人格権は、公表権(作品を公開するかどうか、その時期、方法を決める権利)、氏名表示権(名前を出すか、実名で出すかどうか決める権利)、同一性保持権(著作物を無断で修正されない権利)、名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条11項)があります。
著作権は、複製権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳・翻案権、二次的著作物の利用権などがあります。
二次的著作物の利用権の例としては、「小説をWEBマンガとして連載化した場合に、そのマンガを書籍で販売」したいと考えた場合、出版社は、マンガ作者と原作者双方に、複製の許可をもらう必要があるということです。 -
(4)著作権のルールに違反したらどうなる?
もしあなたやあなたの会社が著作権のルールに違反した場合、それを知った著作者はどのようなアクションを起こす権利があるのかご存じでしょうか。
民事上の権利と、法定刑について解説します。
著作者が持つ、主な民事上の権利となる根拠は、以下の法律が考えられます。- 民法第709条 損害賠償請求
- 著作権法第112条 差止請求
- 著作権法第115条 名誉回復などの措置
著作者は、著作権侵害による損害賠償をはじめ、著作権を侵害している(または侵害しようとしている)行為の差し止めを請求するだけでなく、謝罪広告などの名誉回復を要求することができます。
したがって、著作権の侵害を行った事実を指摘され、被害者である著作者に求められたら、損害賠償金を支払わなければならないだけでなく、不当な引用などにより著作権を侵害した作品やページなどの削除を行い、謝罪文を公開するなど、著作者の名誉を回復するための措置をとらなければなりません。
さらに、著作権侵害罪として処罰を受ける可能性があります。法定刑は、1000万円以下の罰金、または10年以下の懲役です。(著作権法第119条1項)
法人の場合は、3億円以下の罰金を科されます。著作権法違反の法定刑は非常に重いため、企業担当者や経営者は特に注意しておく必要があるでしょう。
なお、ここで科される法定刑で罰金刑が科されたとしても、著作者に対して支払われるものではありません。したがって著作権侵害罪として有罪になれば、科せられる刑罰とは別に、損害賠償金を著作者に対して支払う必要があります。
3、著作権が存在する素材を引用したい場合
では、著作権に違反しないように著作権が存在する素材を利用したいときには、どのようなルールを守るべきなのでしょうか。
-
(1)引用に関する著作権法
著作権法では、引用について第32条1項で規定しています。引用とは、たとえば論文で、ほかの研究者の論文を一部そのまま転記するような行為をいいます。
引用が許可されるためには、一般的に以下の条件を満たす必要があります。- すでに公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道、批評、研究など引用の目的上「正当な範囲内」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
- カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
- 引用を行う必然性があること
- 「出所」を「明示」すること(第48条)
-
(2)正しい引用ルール
上記の要件を踏まえ、一般的に適用されている引用ルールについて、具体的に確認していきましょう。
- 引用元の明記
引用元の著作物名と著作者を明記しましょう。 - 加工しない
引用した部分については、加工などをしてはいけません。 - 引用部分が明確
引用部分が、どこからどこまでかがわかるようにもしなくてはいけません。文章であれば引用符で囲むなどが必要です。 - 引用する分量が自分自身のコンテンツより少ない
自身のオリジナルコンテンツの量よりも、引用の分量が少ないようにしなければいけません。また、自身のコンテンツにその引用が必要であることがわかるようにしましょう。
- 引用元の明記
4、著作権や法律関係の疑問が生じたら、弁護士に相談
社内に法務部を備える余裕がない事業者にとって、著作権は頭の痛い問題かもしれません。
TPP11(環太平洋パートナーシップ協定)の発効により、著作権の保護期間が著作者の死後70年に延期されるなど、著作権に関する状況は日々変化しています。弁護士は法律に関する最新の情報を常にキャッチアップしています。定期的に問題がないかチェックを受けることもおすすめいたします。
すでに著作権侵害の訴えを起こされてしまっている場合も、弁護士に相談してください。賠償請求への対応や、イメージダウンを最小限にとどめるようサポートすることができます。
また、あなたの著作権が他者に侵害されているケースもあります。弁護士は、損害賠償や仮処分申請などを、代理人として請求することも可能です。
5、まとめ
著作権はさまざまな場面で事業活動に影響を与えます。何らかの引用を行う際に、著作権違反にならないか不安な場合は、ベリーベスト法律事務所 大阪オフィスの弁護士にご相談ください。
法律を遵守した引用になるよう、アドバイスをいたします。個別案件のご相談だけでなく、業種・業態に合わせた社内ルールの策定など、包括的なご相談も承りますので、まずはご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|