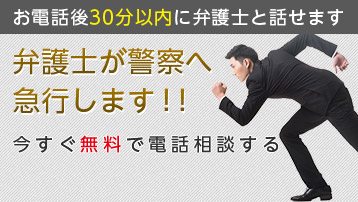偽計業務妨害罪にあたる行為とは? 成立要件と具体例、罰則を解説
- その他
- 偽計業務妨害罪

令和4年9月、大阪地裁は、大学入学共通テストの問題を流出させたとして、偽計業務妨害の非行事実で家裁送致されていた未成年の受験生に対して、保護観察処分とする決定を下しています。本事件では行為の重大性を認識したうえで、深く反省していることなどが考慮されたようです。他方で、共犯の男は同じく偽計業務妨害罪で略式起訴され、罰金50万円の有罪判決が下っています。
偽計業務妨害罪は他人の業務を妨害する罪のひとつですが、どのような行為が処罰の対象になるのかの判断は難しく、この事例のように「偽計にはあたらない」とされるケースも存在しています。このコラムでは「偽計業務妨害罪」が成立する要件や罰則を、具体例を交えながら大阪オフィスの弁護士が解説します。


1、偽計業務妨害罪とは?
どのような行為が偽計業務妨害罪にあたるのかと、刑罰について解説します。
-
(1)偽計業務妨害罪と刑罰
偽計業務妨害罪とは、刑法第233条にて、次のとおり定められています。
(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第233条は、偽計業務妨害罪と信用毀損(きそん)罪の2つの犯罪を同時に規定しています。このなかで偽計業務妨害罪にあたるのは「偽計を用いて人の業務を妨害した」という部分です。
いずれの場合も「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が規定されており、最大で3年にわたる刑務所への収監を言い渡されるおそれがあります(令和7年6月から懲役刑・禁錮刑は拘禁刑となります)。
なお、偽計業務妨害罪の公訴時効は、「3年」と定められています。
公訴時効とは、法律が定めた一定の期間を経過した場合において、犯人を処罰できなくなる制度です(刑事訴訟法第337条4号)。公訴時効の期間については、犯罪の刑罰の重さによって異なります。 -
(2)偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違い
偽計業務妨害罪と同じく、業務妨害罪のひとつとして規定されている犯罪に威力業務妨害罪があります。威力業務妨害罪は、「威力」すなわち、人の自由意思を制圧する程度の勢力を用いて業務を妨害した場合に成立する犯罪です。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は、業務を妨害する手段が違います。偽計業務妨害はうそや不知を利用して業務を妨害する犯罪であるのに対して、威力業務妨害は暴力や威圧的な言動によって業務を妨害する犯罪です。
威力業務妨害罪の罰則も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
2、偽計業務妨害の成立要件
偽計業務妨害罪が成立するための要件は3点です。
「偽計」については判断が難しいため、わかりやすく解説します。
-
(1)偽計を用いること
「偽計」とは次のように解釈されています。
- 人を欺き、誘惑すること
- 人の錯誤や不知を利用すること
- 計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いること
単純には「うそをつく」「虚偽の情報を流す」といった行為が該当しますが、そのほかにも勘違いや不知を利用することも偽計にあたるとされています。また、ここで挙げた要件は「人」に向けられたものですが、人の意思へのはたらきかけを伴わない機械に向けられた行為であっても偽計と判断されるケースがあります。
-
(2)他人の業務を妨害すること
偽計業務妨害罪が成立するためには、「他人の業務への妨害」が必要です。
ここでいう「業務」とは、一般的な「仕事」のイメージにとらわれず、人が社会生活上の地位に基づいて反復・継続する行為を指しています。
利益が生じる企業の活動だけでなく、非営利団体やPTA・同窓会のような組織の活動も業務にあたるため、経済的な利害にとらわれないという点には注意が必要です。
また、実際に業務妨害の結果が生じる必要はなく、業務妨害の危険があるだけでも本罪の成立は妨げられません。この考え方を「抽象的危険犯」といい、加害者が仕掛けた偽計を被害者が看破した場合でも偽計業務妨害罪が成立します。 -
(3)故意があること
偽計業務妨害罪が成立するためには、「偽計を用いること」、「他人の業務を妨害すること」についての故意が必要です。
故意とは、「罪を犯す意思」のことをいいます。これは、犯罪となる事実を認識したうえで、犯罪を実現することを求めたり、やむを得ないと考えたりするように、認容している必要があります。
つまり、偽計業務妨害罪が成立するためには、「偽計を用いること」と「他人の業務を妨害すること」を認識したうえで、認容している必要があります。
お問い合わせください。
3、偽計業務妨害が成立する具体例
偽計業務妨害罪が成立する具体例を挙げていきましょう。
-
(1)いたずら電話や虚偽通報
偽計業務妨害罪が適用される代表的な事例が、いたずら電話や虚偽通報によるものです。
- 携帯電話から119番通報をして、市消防局の消防司令に虚偽の火災発生を告げた【静岡地判平成29年1月31日】
- 合計316回にわたって銀行の窓口に無言電話等をかけた【岡山高判平成28年10月17日】
- 搭乗していた飛行機内で客室乗務員にコロナウイルス感染をほのめかし、運航を遅延させた【千葉地判令和2年11月11日】
-
(2)SNSやネット掲示板におけるデマの流布
SNSやインターネット掲示板などに関連した事件も発生しています。
- 飲食店での飲食写真をSNSに投稿し、「私はコロナだ」「濃厚接触の会」などと投稿した【東京高判令和3年8月31日】
- インターネット上の掲示板に警察官を殺害する旨の虚偽の犯行予告を書き込んだ【東京高判平成25年4月12日】
- インターネット掲示板にJR駅において無差別殺人を行う旨の虚偽の予告を投稿した【東京高判平成21年3月12日】
殺人や爆破などの犯罪予告が典型例ですが、最近は飲食店などのアルバイト従業員を中心に不適切な動画を投稿する、いわゆる「バイトテロ」が問題となるケースも少なくありません。
-
(3)そのほかの事例
過去の事例や判例をみると、人に対する直接的な妨害行為ではなくても偽計業務妨害罪が成立するケースもあります。
- キャッシュカードの暗証番号を盗撮するためにビデオカメラを設置する目的で、営業中のATMを長時間にわたって占拠した【最決平成19年7月2日】
- 競合相手の新聞紙と体裁を似せてシェアを奪おうとした【大判4年2月9日】
- 海上からはわからないように海底に障害物を沈めて漁網を破損させた【大判大3年12月3日】
- 電気メーターを実際の使用量よりも少なくなるように細工した【福岡地判昭和61年3月3日】
- 電話回線にマジックホンを取り付けて課金装置の作動を不可能にした【最決昭和59年4月27日】
- 大学の選抜試験において、マイクロカメラで試験問題を撮影し共犯者から回答を得ようとした【東京地裁立川支部令和4年10月13日】
積極的に虚偽の情報やデマを用いたものではなくても、錯誤や不知を悪用したケースや、機械やデータに不正な改変を加えたケースでは、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
4、偽計業務妨害罪で逮捕された場合の流れ
偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されると、身柄拘束を受けたうえで刑事裁判を受けることになります。
逮捕から刑事裁判への流れをみていきましょう。
-
(1)逮捕による身柄拘束
警察に逮捕されると、警察署の留置場に身柄を置かれたうえで取り調べを受けます。
逮捕を受けた時点から身柄拘束が始まり、自宅へ帰ることも、会社や学校へ通うことも、携帯電話で外部と連絡を取ることも許されません。
警察における身柄拘束の限界は48時間以内です。48時間が経過するまでに、逮捕した被疑者を釈放するか、検察官へと引き継がなくてはなりません。
警察から検察官へと被疑者の身柄・関係書類が引き継がれる手続きを「送致」といいます。
送致を受けた検察官は、自らも被疑者を取り調べたうえで、24時間以内に被疑者を釈放するか、裁判所に勾留を請求しなければなりません。 -
(2)勾留による身柄拘束
裁判官が検察官による勾留請求を認めた場合は、原則10日間以内を限度として身柄拘束が延長されます。勾留を受けることになった被疑者の身柄は警察に戻されて、警察署の留置場に置かれながら検察官による取り調べや検察官の指揮を受けた警察によって捜査が進められます。
10日間以内に捜査が遂げられなかった場合は、裁判官が検察官による請求を認めた場合にはさらに10日間以内の延長が可能です。つまり、勾留による身柄拘束の最長は20日間であり、逮捕後の48時間と24時間をあわせると、逮捕から23日間にわたる身柄拘束を受けることになります。 -
(3)検察官の起訴
勾留が満期を迎える日までに、検察官は起訴・不起訴を決定します。
検察官が起訴をして刑事裁判へ移行することになれば、被疑者は「被告人」へと立場を変えてさらに勾留が続く場合があります。
起訴されて被告人としての勾留が決定した段階からは、一時的な身柄解放である「保釈」の請求が可能ですが、保釈が認められなかった場合は刑事裁判が終わるまで釈放されません。
検察官が不起訴とした場合は、その時点で捜査が終了するため、被疑者の身柄は直ちに釈放されます。 -
(4)刑事裁判での審理
検察官が起訴すると、およそ1〜2か月後に初回の刑事裁判が開かれます。その後はおおむね1か月に一度のペースで裁判が開かれて、最終回となる日には判決が言い渡されます。
実刑判決が下されるとそのまま刑務所へと収監されますが、執行猶予がつけば刑の執行が猶予されるため、社会生活へ復帰できます。また、罰金が言い渡された場合は、裁判所への罰金納付をもって刑罰が終了します。
日本の司法制度では、検察官に起訴されて刑事裁判に発展すると極めて高い割合で有罪判決が下されています。
令和5年の司法統計によると、全国の地方裁判所で開かれた刑事裁判について4万2033件に有罪判決が下されていますが、無罪判決はわずか73件のみでした。有罪率は99.8%となるため、起訴されればほぼ確実に有罪となる事態は避けられません。
このような状況を考えると、厳しい刑罰を回避するには無罪を期待するのではなく、被害者との示談交渉を進めて検察官による起訴を回避するのが最善でしょう。
5、まとめ
いたずら電話での業務妨害や虚偽の110番・119番通報、SNSやインターネット掲示板への犯罪予告の投稿などは、偽計業務妨害にあたります。また、電気・水道メーターに不正な細工を施したり、試験問題を撮影して流出させたりといった行為も同罪に該当する可能性があるため注意が必要です。
業務妨害行為は、企業や団体の活動に支障を来し、多大な損害が発生する可能性があるため、逮捕されるおそれがあります。業務妨害罪の容疑で逮捕された場合には、できるだけ早く弁護士に相談したうえで、早期釈放、不起訴処分を獲得できるように弁護活動を行ってもらうことが重要です。
偽計業務妨害罪にあたる行為をはたらき、逮捕や刑罰に不安を感じているなら、刑事事件の解決実績を豊富にもつベリーベスト法律事務所 大阪オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています