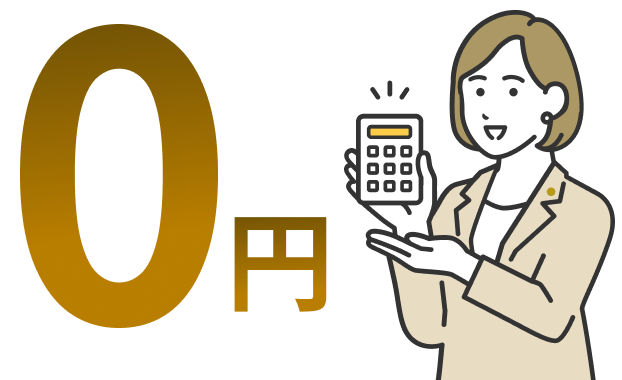効力ある遺言書を残すには? 種類の違いや間違いやすいポイント解説
- 遺言
- 遺言

最近、遺産相続がかかわった事件として、大阪や京都を舞台として起きたいわゆる「後妻業」事件が大きな話題となりました。この事件では、亡くなった男性の遺言書に、後に殺人事件の被告となった妻に全財産を譲る旨記載されていたことが注目を集めました。もちろん全ての遺産相続がこういった事件につながるわけではありませんが、遺産を巡る争いは枚挙にいとまがありませんので、自分の死後に遺産を巡る争いが起きてしまわないように、きちんとした遺言書を残しておきたいと考える方も少なくないでしょう。
しかし、「そもそも遺言書ではどのようなことを決められるのか」「効力のある遺言書とはどのようなものか」など、遺言書についてよくわからないという方も多いのではないでしょうか。遺産を巡る争いを避けるためには、遺言書に関するルールや手続などを正しく理解し、有効かつ、自分の意思をきちんと反映した適切な内容の遺言書を作成しておくことが重要です。
この記事では、有効かつ適切な内容の遺言書を作成するために必要なルールや手続などについて、ベリーベスト法律事務所大阪オフィスの弁護士が解説します。
1、遺言と遺産相続
仮に親から子どもへ遺産を相続させるとした場合、親が「被相続人」、子どもが「相続人」となります。遺言書がなくても、遺産を相続させること自体は可能ですが、被相続人の意思に関係なく民法の規定にしたがって遺産が分けられることになりますし、具体的に誰がどの財産を取得するかなどを相続人の協議によって決める必要があります(これを「遺産分割協議」といいます。)ので、その中で争いが生じる可能性があります。
そこで、被相続人は、法的に有効な遺言書を作成し、だれにどのような財産をどのような割合・方法で相続させるのかをあらかじめ決めておくことにより、自分の死後、財産の取得についての相続人間の争いを避けることが期待できます。また、相続人がもっと財産を欲しいと思っても、遺言書の内容が最優先されますので、被相続人は自分の意思に基づいて遺産を相続させることができます。
相続人としても、遺言書によって遺産が誰に相続されるかが決められていれば、相続人同士の遺産分割協議により決める必要がなくなり、スムーズな相続手続が可能になります。遺言書がなければ、相続人は、現金・預貯金、株式、家・土地など全ての遺産につき、誰がどう取得するのかゼロから話し合わなければなりません。
このように、遺産相続において遺言書があるかどうかは、被相続人にとっても相続人にとっても非常に大きな意味を持っています。もし、あなたが「自分には財産がないから、遺言書はいらない」と思っていたり、「自分の家族は仲が良いので争うことはない」と思っていたりしても、財産の多さや被相続人が亡くなる前の相続人間の関係性にかかわらず、遺産相続を巡る争いが起こる可能性はあります。
あなたの意思に反して、家族が争ったり、余計な手間をかけたりすることをできる限り避けるためには、財産の多さなどにかかわらず、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
2、遺言書で決めることができる内容と効力を知っておこう
では、具体的に、遺言書ではどのような内容を決めることができるのでしょうか。遺言書で決めるべき主な内容とその効力などについてご説明します。
-
(1)相続人に関すること(相続人の廃除等)
誰が相続人になるかについては、民法に、被相続人との身分関係(続柄)に応じた範囲(順位)が定められていますが、 その相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には、法律により一定割合の遺産を相続する権利が最低限保証されています。これを「遺留分」といい、遺留分は遺言によっても奪うことができません。
ただし、被相続人は、相続人から虐待や重大な侮辱を受けていたような場合には、その相続人の相続する権利を失わせることができます。これを「相続人の廃除」といい、被相続人は、遺言において「相続人の廃除」の意思を示すことができます。
なお、「相続の廃除」を行うためには、遺言書で「遺言執行者」を定めておく必要があります。(遺言の効力発生後、「遺言執行者」による家庭裁判所への請求手続が必要になるためです。) -
(2)相続分に関すること
相続人それぞれが遺産を取得する割合(相続分)も、被相続人が遺言によって自由に決めることができます。たとえば、相続人が妻と子ども二人(長男及び次男)であった場合、民法の定めでは、妻が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつの割合で相続することとなりますが、遺言書では、遺産の全部又は一部につき「妻に4分の1、長男に2分の1、次男に4分の1の割合でそれぞれ相続させる」などと決めることができます。
もっとも、いくら遺言で相続分を決められるとしても、(1)で説明したとおり、遺留分を奪うことはできません。 -
(3)遺産分割の方法等に関すること
遺言では、どの財産をどの相続人に取得させるのかなど、遺産分割の方法を定めることができます。また、遺産分割の方法を定めることを第三者に委託することもできます。さらに、相続開始の時から5年を超えない期間で遺産の分割を禁止することもできます。
-
(4)遺贈に関すること
被相続人は、民法により定められた範囲の相続人以外の親族や、内縁の妻、お世話になった知人、慈善団体などなど戸籍上のつながりがない者に対しても、遺言によって遺産を譲ること(これを「遺贈」といいます。)ができます。
-
(5)遺言執行者に関すること
遺言では、遺言の内容を実現するために必要な手続、たとえば預貯金の払戻しや不動産の所有名義変更などを行う者(「遺言執行者」といいます。)を指定することができます。
遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰でも(法人でも)なることができますので、相続人や遺贈を受ける者(受遺者)を指定することもできますし、弁護士や信託銀行などの専門的な第三者を指定することもできます。なお、遺言執行者そのものだけでなく、遺言執行者を指定する者を遺言で指定しておくこともできます。 -
(6)その他身分行為等に関すること
以上のように、遺言では、相続人や遺産の処分にかかる内容を定めるほか、子の認知や未成年後見人の指定などをすることもできます。
-
(7)付言事項
(1)から(6)で述べた内容は、法律上、遺言で定めることが認められた事項(「法定遺言事項」といいます。)であり、遺言に記載されることにより、相続人や受遺者に対する法的な拘束力をもつことになりますので、相続人や受遺者はこれに従わなければなりません。
もっとも、遺言には、法定遺言事項以外でも、葬儀の方法や、「兄弟仲良く助け合い、残されたお母さんを大切にしてほしい」といった相続人らに対する想いなど(付言事項)を記載することもできます。付言事項には法的な拘束力はありませんが、被相続人の意思がより尊重され、円満な相続につながるという可能性もあります。
3、遺言書の種類を知っておこう
法律上効力が認められる遺言の方式(普通方式)としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。また、「危急時遺言」や「隔絶地遺言」といった特別方式の2つ遺言もありますが、これらが使われることはほとんどないといえますので、以下では普通方式の3つの遺言について解説します。
-
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり、被相続人本人が自筆で作成した書面による遺言です。紙(種類は問いません)とペンがあれば、誰でも書きたいときに書くことができ、証人や作成手数料なども不要ですので。遺言の中では最も手軽に作成できるといえます。そのため、遺言書といえば自筆証書遺言をイメージする方も多いのではないでしょうか。
もっとも、法律上有効な自筆証書遺言として認められるためには、被相続人が全文と作成日付及び氏名を自書して押印することが必要であり、ワープロやパソコンで作成されたものは効力がありません。また、加除や変更についても、決められた手順が守られていなければ無効になってしまいます。
また、自筆証書遺言は、相続開始とともに家庭裁判所の「検認」という手続きを受けなければなりません。なお、封印(封筒に入れて糊付けした上で封じ目に印鑑を押すこと)がなくても自筆証書遺言の有効性には関係がありませんが、自筆証書遺言を見つけても「検認」を経ずに勝手に開封してはいけません(過料に処されるおそれがあります)。
自筆証書遺言には、最も手軽に作成できるというメリットがある反面、守るべき要件や手順が守られていないために効力が認められなかったり、偽造や変造がされても気づかれにくかったりするというデメリットがありますので、作成の際には注意が必要です。
遺言書の内容を確実に実現するためには、弁護士などの専門家に相談や依頼をして作成するとともに、場合によっては保管も依頼しておくことをおすすめします。 -
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人と呼ばれる法務大臣に任命された公務員が作成した書面(公正証書)による遺言です。公証人が遺言内容を確認し、法律の定めに従った書き方・手順で作成して保管もしてくれるため、最も確実に効力が認められる方式の遺言といえます。遺言に必要な意思能力が認められれば、自筆ができない方でも作成可能です。
もっとも、作成時には2名の証人が必要となり、相続財産の金額等に応じた所定の手数料はかかりますが、家庭裁判所での検認手続は不要です。
ただし、被相続人も、誰にどのような財産を相続させるかといった遺言の内容自体は自身で考えたうえで、具体的な文面につき公証人と打ち合わせをする、関係書類をそろえるといった準備が必要になりますので。公正証書遺言の作成についても、弁護士などの専門家に相談や依頼をしたほうがよいといえるでしょう。 -
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で公証人と2名の証人に遺言書の存在を証明してもらいつつ、その内容については、公証人や証人に確認させずに「秘密」にするという形式の遺言です。
秘密証書遺言においては、封印された遺言書が公証人及び証人に提出され、これに公証人らが日付等の記載や署名・押印をすることにより「遺言書がある」という事実を証明するだけであって、公証人は遺言書の作成には一切関わりません。
そのため、秘密証書遺言では、遺言の内容を秘密にしつつ、遺言の存在自体が明らかにならないまま相続手続が進行してしまうという可能性を自筆証書遺言に比べて減少させることはできますが、遺言書自体に署名押印が無い場合や遺言書内と封筒の封印で印影が異なる場合などに無効となるリスクがあります。
また、秘密証書遺言では、公正証書遺言と同様に、証人の確保と所定の手数料が必要となります。他方で、自筆証書遺言と同様に、相続開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となりますので、検認の前に開封してはいけません。
上記のような事情から、秘密証書遺言の利用件数は少ないといえるでしょう。秘密証書遺言の作成を考えた際も、遺言の内容や作成・保管に関して、あらかじめ弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
4、遺言書が無効になる場合を知っておこう
遺言の内容については、効力発生時すなわち相続開始時には、遺言者(被相続人)は死亡していますので、遺言者にその真意を確認するということはできません。
そのため、法律は、遺言によって生じる権利関係が不明確にならないよう、遺言で定めることのできる事項を限定しており、それ以外の事項(付言事項)には法的拘束力を認めていません(記載してはいけないということではありません)。
そして、遺言の記載内容に誤りや不明確な部分がある場合には、その内容には効力が認められないと判断されることも多いうえ、法律は、遺言が有効となるための要件や手順・手続を厳格に定めており、これらを満たしていない場合には、遺言そのものが無効とされてしまうことになります。
法律上、遺言(主に自筆証書遺言)そのものが無効になる事由としては、以下のようなものがありますので、あらかじめ知っておきましょう。
-
(1)被相続人が有効に遺言を行う能力を有していない
民法第961条によって、15歳に達した者は遺言が可能とされていますので、15歳未満の者による遺言は無効です。逆に、たとえ未成年でも15歳以上の者が作成した遺言書であれば、保護者でもその内容を変更したり取り消したりすることはできません。
また、民法上の意思能力(事理弁識能力)がなければ、有効に遺言を行うことはできないと考えられますが、成年後見人が就任している成年被後見人については、一時的に事理を弁識する能力が回復したときには、2名以上の医師の立ち会い等により、遺言書を作成することができます(民法第973条)。 -
(2)2人以上の者や第三者が関わっている
民法975条は、2人以上が同一の書面で遺言を作成すること(「共同遺言」といいます。)はできないとしており、共同遺言は作成されても無効となってしまいます。また、遺言者(被相続人)以外の第三者が代わりに作成した遺言も無効です。遺言書は、遺言者(被相続人)本人が単独で作成する必要があるのです。
-
(3)決められた作成手順が守られていない
すでに触れたとおり、自筆証書遺言には法律で定められた手順があり、これに従って作成しなければ無効となってしまいます。自筆証書遺言が無効になるケースとしては、全文を自書するのではなく、パソコンで本文を作成し、署名押印だけ手書きで行っていたケースや、作成日付の記載がない、あるいは「平成○年○月吉日」など日付の特定ができないといったケースが多いように思われます。
5、まとめ
今回は、遺言について、その種類・内容・効力などのポイントをご説明いたしました。
自分の死後、相続人同士の争いを避け、自分の意思に沿った遺産相続を実現するためには、遺言書を作成しておくことが効果的です。また、その遺言書を有効とするために必要な要件を満たし、適切な手順・手続を踏むことが重要です。
広く利用される自筆証書遺言ですが、法律に定められたルールに沿っていないために無効になるケースが多々ありますし、せっかく作成した遺言書が未発見のまま、遺産相続が進んでしまう可能性もあります。そのため、できるかぎり確実に有効な遺言を作成したいという方にとっては、公証人が遺言内容を確認し、法律の定めに従った書き方・手順で作成して保管もしてくれる公正証書遺言の利用が望ましいのではないでしょうか。
もっとも、公正証書遺言であっても、遺言者(被相続人)自身が自分の意思をより確実に実現するための遺言内容を考え、具体的な文面につき公証人と打ち合わせをする、関係書類をそろえるといった準備をしなければなりません。
そこで、公正証書遺言をはじめとする遺言作成を検討している方には、弁護士などの専門家に相談や依頼をおすすめします。遺言作成にかぎらず遺産相続に関する不安などがある方についても同様です。そして、弁護士などへの相談や依頼を考えている方はぜひベリーベスト法律事務所大阪オフィスまでご連絡ください。相続問題の対応経験が豊富な弁護士が、親身になってアドバイスやサポートをさせていただきます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています